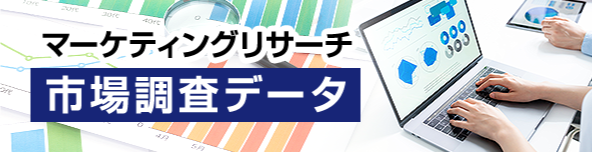青森県 の博物館(17施設)
青森県にある博物館の一覧です。
博物館は、恐竜や日本刀など様々な分野で文化的・資料的価値の高い品が展示される施設です。旅探たびたんでは口コミ投稿数などをもとに、青森県の博物館をランキング順で掲載。面白い博物館や人気の博物館が簡単に見つかります。「行ってよかった展覧会を知りたい」「子供と一緒に楽しみたい」という方は、旅探がおすすめです!博物館一覧は、①アクセス数、②動画、③写真、④口コミの多い順に掲載しています。
※施設までの距離は、直線距離から算出し表示しております。直線距離の確認・目安としてご活用ください。
実際の正確な道路距離・所要時間・経路については「施設までの徒歩経路」ボタンをクリックし、「Googleマップ」にてご確認をお願いします。

東北地方
- 青森県の博物館
- 17施設
- ランキング順
-
-
私立
立佞武多の館
所在地: 〒037-0063 青森県五所川原市大町506-10
- アクセス:
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 青森県五所川原市にある立佞武多の館は高さ23m、重さ19トンにもなる巨大な人形灯籠が見れる場所です。2024年11月に行って来ましたが、6階建ての建物の中にスッポリと収まっており、そのまま街へ動き出せる様になってました。迫力満点です。2025年は大規模改修工事のため、4月1日から2026年6月末まで休館となるそうです。あともう少しの営業でしばらく見れなくなりますよ!館内の展示室は吹き抜けとなっておりエレベーターで4階まで上がり、展示物の周りを螺旋状のスロープでグルグル回りながら降りてくる様になってます。中心部には高さ23mの立佞武多が3体有り、螺旋状の壁にはその歴史やねぷた祭りについて詳しく案内されています。これだけ高いねぷたを作るのに、現代の技術ではなんとなく分かりますが、昔の時代に良く作れたなと感心させられます。ねぷた祭りと言っても青森には各地域によって形は様々で横に大きく広がる青森ねぷたや丸い半円の中に形取った弘前ねぷたなど、青森全域で見られます。是非、各地のねぷた祭りも見てください。
-
所在地: 〒038-0012 青森県青森市柳川1丁目112-15
- アクセス:
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸は、青森県青森市に位置する歴史的な博物館船です。この船は、かつて青森と函館を結ぶ青函連絡船として活躍していました。八甲田丸は1964年に建造され、1988年まで運航されておりました。青函トンネルの開通によりその役割を終えた後、1990年に博物館として公開されました。 八甲田丸は、津軽丸型の第2船として建造され、総トン数は約8,313トン、全長132メートル、全幅17.9メートルの大型船です。最大速力は20.93ノットで、旅客定員は1,200名でした。この船は、青函連絡船の中でも最も長い23年7か月間運航され、多くの乗客と貨物を運びました。 現在、八甲田丸は青森市の文化交流施設として、特定非営利活動法人あおもりみなとクラブによって管理運営されております。船内は地下1階から4階まであり、各階にはさまざまな展示が行われております。1階の車両甲板には、かつて北海道で特急として使用されたキハ82形気動車や郵便車が展示されております。2階の船楼甲板には、乗船口や受付カウンター、飲食スペースがあり、3階の遊歩甲板には津軽海峡文化コーナーや青函連絡船記念館があります。4階の航海甲板には操舵室や通信室があり、煙突は展望台として利用されており、青森港や青森市内の景色を楽しむことができます。 また、館内には立体映像や模型を使って青函航路の歴史を紹介する展示があり、運航のシミュレーションゲームやパソコンクイズなども楽しめます。さらに、解体された羊蹄丸から移設された「青函ワールド」という原寸大ジオラマも展示されており、往年の青森の街並みを再現しております。 八甲田丸は、青森ウォーターフロントの中心施設として、地域の観光資源としても重要な役割を果たしています。青森港を訪れる際には、ぜひこの歴史的な船を訪れてみてください。青函連絡船の歴史とともに、当時の航海の雰囲気を体験することができるでしょう。
-
公立
青森市森林博物館
所在地: 〒038-0012 青森県青森市柳川2-4-37
- アクセス:
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 青森市森林博物館は、青森県青森市に位置し、1982年に開館しました。この博物館は、郷土・青森を軸に、緑の大切さや森林と人間の結びつきをテーマにしております。子どもからお年寄りまでが楽しみながら学習できるように工夫されており、地域の自然や文化を深く理解することができます。 博物館の建物は、主に県産ヒバ材を使用したルネッサンス式木造建築で、その美しい外観は訪れる人々を魅了しております。この建物は、1908年に青森大林区署(のちの青森営林局)庁舎として建設されましたが、営林局庁舎が新築される際に青森市が旧庁舎の本館部分を保存し、博物館として転用しました。現在では、青森市の指定有形文化財となっております。 博物館の展示は多岐にわたり、8つの展示室があります。第1展示室「森と仲間たち」では、森林に棲む小動物や森の生態系、樹木の働きについて学ぶことができます。第2展示室「木と暮らし」では、森林資源の現状や木材の利用方法、森林と人間の関わりについて展示されております。第3展示室「雪とスキー」では、青森県のスキーの歴史や森林管理に利用されたスキーの実物が展示されております。 第4展示室「青森とヒバ」では、ヒバの生理・生態・分布と特徴、ヒバ材利用の歴史について学ぶことができます。第5展示室「津軽森林鉄道」では、津軽森林鉄道の歴史や運行に関する展示があり、当時の木材流通の様子を知ることができます。第6展示室「森を育てる」では、森林を守り育てる仕事や森林の公益機能について学ぶことができます。 また、別館(第7展示室)では、実際に下北半島の森林鉄道で活躍した機関車が展示されています。この機関車は、映画「飢餓海峡」のロケでも使用されました。特別室「旧営林局長室」では、映画「八甲田山」のロケにも使われた明治の雰囲気を残す部屋が公開されております。 博物館の前庭には、明治・大正に植樹された外国種のヒッコリーやアメリカトネリコ、本県産のヒノキアスナロ(ヒバ)、ソメイヨシノなど約100種、約300本の木々が植えられており、四季折々の風景を楽しむことができます。 青森市森林博物館は、青森駅から徒歩約10分の場所にあり、アクセスも便利です。家族連れや観光客にとって、青森の自然と歴史を学ぶ絶好のスポットとなっています。ぜひ訪れてみてください。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 海底240m、総延長53.85km、津軽海峡の海底を貫く海底トンネル。構想から開通まで42年、過酷な条件の中で繰り広げられた数々の軌跡を、当時の資料をもとに音や映像、立体モデルなどを交えて、わかりやすくご紹介している場所です。また、海底下140mの世界を体験できる体験坑道へは青函トンネル龍飛斜坑線もぐら号に乗り込んで斜度14度の斜坑を、わずか7分で案内してくれます。今も利用されている地下坑道の一角に、特設展示エリアを設け実際に掘削に使われた機械や器機などを展示、当時の現場を再現展示しています。体験ツアーの所要時間は約40分、世界へ誇る大事業を是非体感してみて下さい。前後間もない1946年から地質調査開始、1964年掘削開始、1985年貫通、1988年線路の開通、2016年北海道新幹線開通。冬場は雪の為営業は行われてません。令和7年は4月18日より開業予定です。 青森駅から車で約100分くらいはかかります。
-
私立
太宰治記念館「斜陽館」
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 青森県五所川原市にある太宰治記念館・斜陽館、太宰治の父は地元の大地主で明治40年に入母屋作りの木造2階建て、当時は、衆議院議員であった父親とその家族、太宰治も一緒に住んでいたそうですが、父親は東京への出張などであまり家に居ることはなく、太宰治も中学校までと短い住まいでした。戦後、昭和25年には津島家は町内の旅館経営者へ家を売却ししばらくは旅館として成り立ってましたが、その後、経営悪化のため、1996年に町が買取りし、平成10年から太宰治記念館として津島家の成り立ちや太宰治の生い立ち、経歴など資料館としてもいろいろ展示されてます。明治40年に建てられた建物としては内装に洋室が取り入れられ、レンガ積みや応接室など今見てもすごく立派な作りとなっています。時期により多少違いますが9:00〜17:00大人600円、高大400円、小中250円、道路を挟んでお土産屋さんと駐車場有り。太宰治と建築に興味がある方には必見です。
-
私立
高岡の森 弘前藩歴史館
所在地: 〒036-1344 青森県弘前市高岡字獅子沢128-112 高照神社南隣接
- アクセス:
「「高岡」バス停留所」から「高岡の森 弘前藩歴史…」まで 徒歩2分
津軽岩木スカイライン「8合目駐車場出入口(IC)」から「高岡の森 弘前藩歴史…」まで 6.3km
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 高岡の森弘前藩歴史館は、青森県弘前市高岡に位置する場所にあります。 平成30年(2018年)4月1日に開館いたしました。この歴史館は、弘前藩の歴史と文化を後世に伝えるために設立されました。弘前藩は、江戸時代に弘前市を中心に栄えた藩で、津軽氏が治めておりました。 歴史館の展示内容は、弘前藩に関連する貴重な資料や品々を中心に構成されております。例えば、初代藩主、津軽為信が豊臣秀吉から拝領したと伝わる「太刀 銘 友成作」や、四代藩主、津軽信政の遺品、明治時代に津軽家や旧藩士たちが高照神社に納めた武具刀剣類などが展示されております。これらの展示物は、弘前藩の深い歴史や文化を深く理解するための貴重な資料となります。 館内には、弘前藩の成り立ちや津軽家の歴史、地域文化について学べる展示が多数あります。例えば、弘前城と高照神社、岩木山などの位置関係がしっかりわかる地形模型や、津軽信政の葬送行列を描いた絵巻を見ることができるタッチパネルなどが設置されております。これにより、訪れる人々は視覚的に歴史を学ぶことができます。 また、歴史館では年に数回、テーマに沿ったイベントや展示替えが行われております。これにより、訪れるたびに新しい発見があり、何度でも楽しむことができ、新たな知識の習得ができます。最近のイベントでは、「高照神社展」などが開催され、多くの来館者を魅了いたしました。 施設の概要としては、鉄筋コンクリート造と一部鉄骨造の2階建ての建物で、建築面積は1,700.70平方メートル、延床面積は1,636.56平方メートルです。展示面積は396.06平方メートル、収蔵面積は521.80平方メートルで、約5,300点の多くの資料が収蔵されています。 高岡の森弘前藩歴史館は、弘前藩の歴史や文化を学びつつ、現代に残された貴重な宝物を厳かな空間で見ることができる大切な場所となります。青森県を訪れた際には、ぜひ足を運んでみてください。歴史と文化に触れる貴重な体験が待っています。
-
公立
八戸市博物館
所在地: 〒039-1166 青森県八戸市大字根城東構35-1
- アクセス:
- 投稿ユーザーからの口コミ
- こちらの博物館は八戸市を代表する八戸市博物館です。 JR八戸線「長苗代」下車 徒歩18分のところに位置しています。 ここは常設展の展示の数が豊富で、縄文時代からの八戸市の考古学的資料が豊富にそろっています。 いくつか紹介すると、 考古展示室、こちらは、縄文時代、人びとは、シカやイノシシなどの動物や、魚や貝、木の実などを採ったり、農耕を行って暮らしていました。 考古展示室では、縄文時代から根城南部氏が活躍する中世までの八戸の様子を紹介しています。 歴史展示室、こちらは、寛文4年(1664)、八戸藩2万石が誕生し、現在の三八公園のところに八戸城を構えました。以後城下町の整備が行われ、現在の八戸の中心街の基礎が作られました。江戸時代の八戸藩の様子を紹介しています。 民俗展示室、こちらは、厳しい風土の中で、八戸の人々は知恵と努力により、たくましく生きてきました。現在の発展を築いてくれた先人たちの生活の様子を、衣食住・農業・漁業・商業・信仰・芸能などの資料で紹介しています。 無形資料展示室、こちらは、最近リニューアルしました。元は再生用の機械をタッチパネル式に交換し、これまで音声中心だった展示に映像が加わりました。 展示内容はこれまでの昔話、民謡、わらべ唄、方言に加え、八戸市の小中学校の校歌、芸能、祭り、観光を新たに追加。八戸の魅力を余すところなく伝えます。 また、ここの目玉は、国指定重要文化財「丹後平古墳群出土品」です。 平成30年(2018)10月31日、八戸市にある国史跡「丹後平古墳群」の出土品195点が、国の重要文化財に指定されました。出土品を永く保存するため、保存修理を進めながら常設展示を行っています。 この展示は国の重要文化財ですので大変見応えがあります。 この、八戸市博物館は、縄文時代の展示から江戸時代の藩の資料や各時代時代で暮らしてきた人々の衣食住の様子等幅広い八戸市の歴史を知ることができる貴重な博物館です。
-
公立
弘前市立観光館
所在地: 〒036-8356 青森県弘前市下白銀町2-1 追手門広場内
- アクセス:
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 弘前市観光館は、青森県弘前市の中心部に位置しております。観光情報の提供や地域文化の紹介を行う施設となります。弘前公園のすぐそばにあり、観光の拠点として多くの観光客に利用されています。観光館は、弘前市とその周辺地域の観光情報を提供するだけでなく、地元の伝統工芸品や文化を紹介する展示も行っております。 観光館の1階には、弘前ねぷたまつりで使用される「組ねぷた」が展示されております。これは、津軽の夏の夜を彩る重要無形民俗文化財であり、訪れる人々にその迫力と美しさを伝えております。また、1階にはお土産コーナー「さくらはうす」があり、津軽塗やこぎん刺し、ブナコなどの伝統工芸品や、リンゴジュースやアップルパイなどの地元特産品を購入することができます。 2階には、津軽塗の制作過程を紹介するコーナーがございます。津軽塗は、津軽藩4代藩主・信政公の時代に始められた伝統的な工芸品で、木地から塗り・研ぎまでの48工程をわかりやすく展示しております。また、津軽の風土に育まれた民工芸品も一堂に展示されており、津軽の春夏秋冬を感じることができるスペースです。 観光館では、定期的に特別展示やイベントも開催されております。例えば、「古津軽ウィーク」では、地域の歴史や文化をテーマにした展示や体験イベントが行われ、多くの来館者を魅了しております。また、弘前市出身の作曲家、菊池俊輔の功績をたたえる常設展示もあり、彼の遺品や愛用のピアノ、ゴールドディスクなどが展示されています。 観光館の施設概要としては、鉄筋コンクリート造の2階建てで、広々とした展示スペースと多目的ホールがございます。多目的ホールは、観光物産展や講演会、研修会などに利用されており、地域の交流の場としても機能しております。 観光館の開館時間は午前9時から午後6時までで、まつり期間中は延長されることもあります。休館日は年末年始で、臨時開館する場合もあります。観光案内カウンターでは、弘前市と周辺エリアの観光情報やパンフレットを提供しており、散策プランの相談や情報収集に役立ちます。 弘前市観光館は、地域の歴史や文化を学びながら、観光情報を得ることができる貴重な施設です。弘前市を訪れた際には、ぜひ立ち寄ってみてください。新しい発見と感動、様々な体験が待っています。
-
公立
田舎館村博物館
所在地: 〒038-1111 青森県南津軽郡田舎館村大字高樋大曲63
- アクセス:
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 田舎館村博物館は、青森県南津軽郡田舎館村に位置する歴史と文化を深く学べる施設となります。この博物館は、田舎館村埋蔵文化財センターと併設されており、両施設を共通料金で見学することができます。 田舎館村博物館の主な展示内容は、弥生時代から現代に至るまでの地域の歴史と文化を紹介するものです。特に注目すべきは、垂柳遺跡と高樋遺跡に関する展示です。垂柳遺跡は、弥生時代の北限の水田跡として国の史跡に指定されており、約2,100年前の水田跡や水路跡がそのまま保存されております。この遺構露出展示室では、広さ140㎡の水田跡を自由に歩くことができ、当時の農業の様子を体感することができます。 また、高樋遺跡から出土した炭化米や深鉢形土器、石斧などの県重要文化財も展示されております。これらの展示物は、地域の歴史や文化を理解する上で非常に貴重な資料となっています。 田舎館村博物館は、地域の歴史を学ぶだけでなく、訪れる人々にとっても楽しめる施設となります。博物館内には、カフェやレストランも併設されており、ゆったりとした時間を過ごすことができます。また、博物館の周辺には、田んぼアートや展望台などの観光スポットも点在しており、訪れる価値があります。 アクセスも便利で、弘南鉄道「田舎館」駅から徒歩約15分、JR「川部」駅から車で約15分の距離にあります。また、青森市から車で約60分、弘前市から車で約20分と、県内各地からのアクセスも良好です。 田舎館村博物館は、地域の歴史と文化を深く学び、楽しむことができる場所です。ぜひ一度訪れてみてください。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- ツカハラミュージアムは、青森県八戸市に位置するクラシックカーの博物館で、世界中から集められた名車の数々を展示しております。この博物館は、車好きや歴史愛好家にとって魅力的なスポットであり、訪れる人々に車の歴史と技術の進化を伝えております。 ツカハラミュージアムの展示車両は、トヨタ2000GT、ロールスロイス・シルバーゴースト、フォード・モデルT、ルノー35CVなど、かつて時代の最先端を駆け抜けた名車が揃っています。これらの車両は、外観だけでなくエンジンや内部のパーツに至るまで丁寧に修復されており、その技術力と情熱が感じることができます。 博物館の設立者である塚原氏は、自動車の部品販売や電気修理業からスタートし、長年にわたりクラシックカーの修復に情熱を注いできました。彼のビジョンは、車を単なる移動手段としてではなく、歴史的文化遺産として捉え、その価値を次世代に伝えることとなります。ツカハラミュージアムでは、修復作業の現場を見学することができ、ネジ一本、パーツ一つ一つにこだわる職人技を間近で見ることができます。 また、ツカハラミュージアムは、子どもたちに物作りの大切さと技術の伝承を目的とした教育プログラムも実施しております。これにより、若い世代が車の歴史や技術に触れ、興味を持つきっかけを提供しています。博物館内には、幻のフォーミュラニッポン試作車の座席に座ることができる展示コーナーもあり、訪れる人々にとって貴重な体験となっております。 ツカハラミュージアムは、クラシックカーの美しさと技術の粋を堪能できる場所であり、車の歴史に興味がある人々にとって必見のスポットとなります。訪れる人々は、展示車両を通じて過去の車文化に触れ、その進化の過程を学ぶことができます。さらに、修復作業の現場を見学することで、物作りの大切さと技術の継承の重要性を実感することができます。 この博物館は、地域の文化財としての役割も果たしており、地元の誇りとなっております。ツカハラミュージアムを訪れることで、車の歴史と技術の進化を深く理解し、その魅力を再発見することができるでしょう。
-
-

-

- 0枚
-
-

-

- 0本
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 十二湖エコミュージアムセンター「湖郷館」は、青森県西津軽郡深浦町に位置し、世界自然遺産である白神山地の麓にあります。この施設は、訪れる人々に白神山地と十二湖の自然の美しさと重要性を伝えることを目的としております。 湖郷館では、白神山地の豊かな生態系や歴史、文化について学ぶことができます。館内には、白神山地の自然を紹介するハイビジョン映像や、十二湖の成り立ちを示すジオラマなどが展示されております。これらの展示物は、子供から大人まで楽しめる内容となっております。訪れる人々に自然の魅力を伝えています。 また、湖郷館の周辺には遊歩道が整備されており、自然観察や散策を楽しむことができます。観察小屋も設置されており、四季折々の自然の変化を間近で感じることができます。特に、十二湖の一つである青池は、その美しいブルーの世界が訪れる人々を魅了いたします。 湖郷館は、自然保護と環境教育の拠点としても重要な役割を果たしております。ここでは、自然環境の保全活動や、地域の自然資源を活用した教育プログラムが実施されております。これにより、訪れる人々は自然との共生の大切さを学び、環境保護への意識を高めることができます。 さらに、湖郷館は地域の観光拠点としても機能しており、訪れる人々に深浦町の魅力を伝える役割も担っています。地元の特産品や工芸品の展示・販売も行われており、地域経済の活性化にも寄与しております。 十二湖エコミュージアムセンター「湖郷館」は、自然の美しさとその保護の重要性を伝えるだけでなく、訪れる人々に深浦町の魅力を紹介する場として、多くの人々に愛されております。自然と触れ合いながら、白神山地と十二湖の素晴らしさを体感できるこの施設は、訪れる価値のある場所です。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 中泊町博物館は、青森県北津軽郡中泊町に位置し、地域の歴史や文化を深く知ることができる施設です。この博物館は、津軽半島の自然、歴史、民俗、産業に関する幅広い展示を行っており、訪れる人々に地域の魅力を伝えております。 博物館の常設展示では、津軽半島の原始時代から近現代までの歴史を網羅しております。特に、考古学的な遺物や古代の生活様式を再現した展示は、訪れる人々に当時の生活をリアルに感じさせます。また、地域の産業の発展や伝統工芸品の展示もあり、津軽の文化と技術の進化を学ぶことができます。 中泊町博物館は、四季折々の企画展も開催しており、季節ごとに異なるテーマで地域の魅力を紹介しております。これにより、何度訪れても新しい発見があり、リピーターも多い博物館です。例えば、春には地元の花や植物に関する展示、夏には海や漁業に関する展示が行われることが多いです。 博物館の周辺には、観光スポットも多く点在しております。例えば、中泊町特産物直売所「ピュア」では、地元の新鮮な農産物や特産品を購入することができます。また、吉田松陰遊賞之碑や大沢内ため池など、歴史的な名所や自然の美しい景観を楽しむことができるスポットもあります。 中泊町博物館は、地域の教育機関としても重要な役割を果たしております。地元の小中学生や65歳以上の高齢者は、入館が全日無料で、地域の歴史や文化を学ぶ場として活用されています。また、博物館では、地域の歴史や文化に関する講座やワークショップも定期的に開催されており、地域住民の学びの場としても機能しております。 さらに、中泊町博物館は、地域の文化財の保護と保存にも力を入れています。博物館内には、地域の重要文化財や歴史的な遺物が多数収蔵されており、これらの貴重な資料を後世に伝えるための活動が行われております。特に、宮越家住宅の保存と公開は、地域の歴史を知る上で重要な取り組みの一つです。 中泊町博物館は、地域の歴史と文化を深く学び、体験することができる貴重な施設です。津軽半島の豊かな自然と歴史を感じながら、地域の魅力を再発見することができるこの博物館は、訪れる価値のある場所です。ぜひ一度足を運んでみてください。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 新渡戸記念館は、青森県十和田市に位置し、日本を代表する国際人であり教育者であった新渡戸稲造博士の功績を称えるために設立された博物館となります。この記念館は、博士の遺品や新渡戸家に伝わる貴重な資料を展示し、訪れる人々に新渡戸稲造の生涯とその思想を紹介しております。 新渡戸稲造博士は、著書『武士道』で知られ、国際連盟事務次長としても活躍しました。記念館では、彼の生涯を通じて培われた思想や哲学を学ぶことができます。展示品には、博士の書簡や日記、愛用の品々が含まれており、彼の人となりを感じることができます。また、新渡戸家に代々伝わる甲冑や武具も展示されており、武士道の精神的源流を垣間見ることができます。 記念館の建物自体も歴史的価値があり、1965年に新渡戸家の協力のもとに建設いたしました。2024年には耐震性の確認が完了し、安全に訪れることができる施設となっています。また、記念館は地域の文化財の保護と保存にも力を入れており、地域の歴史や文化を後世に伝える重要な役割を果たします。 新渡戸記念館では、定期的に企画展や特別展が開催されており、訪れるたびに新しい発見があります。例えば、新渡戸稲造の思想や業績に関する展示だけでなく、地域の歴史や文化に関する展示も行われております。これにより、地域の魅力を再発見することができ、多くのリピーターが訪れます。 さらに、記念館は教育機関としても機能しており、地元の学校や団体との連携を通じて、教育プログラムやワークショップを提供しています。これにより、地域の子供たちや住民が新渡戸稲造の思想や地域の歴史を学ぶ機会を提供しております。 新渡戸記念館は、地域の観光拠点としても重要な役割を果たしています。訪れる人々は、記念館を通じて十和田市の歴史や文化を深く知ることができ、地域の魅力を再発見することができます。また、記念館の周辺には美しい自然景観や歴史的な名所が点在しており、観光客にとっても魅力的なスポットとなっています。 新渡戸記念館は、訪れる人々に新渡戸稲造の偉業とその思想を伝えるだけでなく、地域の歴史や文化を深く学ぶことができる貴重な施設となります。ぜひ一度足を運び、新渡戸稲造の世界に触れてみてください。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 大畑線キハ85動態保存会は、青森県むつ市大畑町に位置する鉄道保存団体となります。かつて本州最北端の鉄道駅として知られた大畑駅を拠点としております。この団体は、2001年に廃線となった大畑線のキハ85形気動車を動態保存し、定期的に運転会を開催しております。 大畑線は、かつては下北交通が運営していた鉄道路線で、むつ市大畑町と下北半島の他の地域を結んでおりました。廃線後、多くの鉄道ファンが訪れ、その歴史的価値を認識した地元などの有志たちが動態保存のために立ち上がりました。大畑線キハ85動態保存会は、関東地方在住の鉄道愛好者たちによって運営されており、旧大畑駅構内の約500メートルの線路を使用して運転会を行っております。 キハ85形気動車は、旧国鉄時代のキハ22形を改造したもので、2両が動態保存されております。1両は旧国鉄色、もう1両は下北交通色に塗装されており、訪れる人々に懐かしい昭和の鉄道風景を提供しています。また、静態保存されているキハ85-1の車内にはHOゲージの鉄道模型レイアウトが設置されており、定期運転会の際に公開されています。 運転会は毎年5月から10月の第3日曜日に開催しています。訪問者は国鉄時代の切符を復刻した会員証と1日乗車券を購入して乗車体験を楽しむことができます。運転会では、キハ85形気動車が旧大畑駅構内を往復し、約15分間の乗車体験が提供されております。体験料は200円で、1日に何度でも乗車可能です。 大畑線キハ85動態保存会の活動は、地域の観光振興にも寄与しています。むつ市大畑町は、秘湯温泉や露天風呂、紅葉、桜、祭り、グルメなど多彩な観光資源を持つ豊かな地域であり、鉄道保存活動を通じて訪問者を引き寄せます。また、地元の観光協会とも連携し、地域の魅力を発信する取り組みを行っております。 このように、大畑線キハ85動態保存会は、鉄道遺産の保存と地域振興を両立させる貴重な存在です。訪れることで、昭和の鉄道風景を体験し、地域の歴史や文化に触れることができます。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 二ツ森貝塚館は、青森県七戸町に位置する縄文時代の貝塚遺跡で、約5,500年前から4,000年前にかけて栄えた集落の一部となります。この遺跡は、1998年に国の史跡に指定され、2015年にはさらに広範囲が追加指定されました。2021年には北海道・北東北の縄文遺跡群として世界文化遺産に登録されました。 二ツ森貝塚は、太平洋岸の小川原湖西岸に位置しており、標高30メートルの段丘上に広がっています。遺跡の広さは東西約600メートル、南北約170メートルの範囲であり、貝塚の厚さは約1.5メートルに達します。貝塚からは、貝類のハマグリやホタテ、ヤマトシジミなど、魚類のスズキやマダイ、フグなどの魚骨、ハクチョウやカモなどの鳥骨、シカやイノシシなどの獣骨が出土しております。 竪穴建物跡や貯蔵穴が多数見つかっております。大規模な集落であったことが想像できます。特に、鹿角製の櫛や鯨骨製の青竜刀型骨器など、精巧に加工された骨角器が出土しております。当時の人々が高い加工技術力を持っていたことを示しています。 二ツ森貝塚館は、旧小学校の一部を改修して2021年にオープン致しました。この施設では、二ツ森貝塚から出土した土器や石器、獣骨などを展示しております。縄文時代の人々の生活を垣間見ることができます。また、貝層断面の剥ぎ取りや出土品の展示を通じて、当時の環境や生業について学ぶことができます。 二ツ森貝塚館は、青森県上北郡七戸町字鉢森平181-26に位置します。東北新幹線の七戸十和田駅から車で約20分、青い森鉄道の上北町駅から車で約10分の距離となります。開館時間は10:00から16:00となります。休館日は月曜日と祝日の翌日、年末年始はお休みとなります。 ここ二ツ森貝塚館は縄文時代の生活や環境を学ぶ上で非常に貴重な施設です。訪れることで、当時の人々の暮らしや技術、自然環境への適応の様子を深く理解することができます。
-
公立
旧制木造中学校講堂
所在地: 〒038-3138 青森県つがる市木造若緑52
- アクセス:
JR五能線「木造駅」から「旧制木造中学校講堂」まで 徒歩11分
津軽岩木スカイライン「8合目駐車場出入口(IC)」から「旧制木造中学校講堂」まで 18.7km
-

-

- 0枚
-
-

-

- 0本
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 旧制木造中学校講堂は、青森県つがる市に位置する歴史的建造物で、昭和4年(1929年)に建設されました。この講堂は、当初青森県立木造中学校の講堂として使用され、その後、戦後には木造高等学校の校舎として利用されました。さらに、中央公民館の講堂としても転用され、地域の学習や文化活動の場として親しまれてきました。 この講堂は、つがる市指定文化財として保存されております、平成29年(2017年)には解体調査が行われ、翌年から現在地への移築復元が実施されました。令和2年(2020年)3月に工事が完了し、現在では多目的ホールとして利用されております。講堂の構造は木造モルタル平屋建で、鉄板瓦棒葺きの半切妻屋根を持ち、建築面積は332.89平方メートルです。 講堂の歴史は、地域の教育と深く結びついております。青森県立木造中学校は、明治35年(1902年)に創立され、地域の教育熱心な住民によって支えられてきました。講堂は、入学式や卒業式などの学校行事の場として使用され、また、来賓による講演会も開催されました。戦後の学制改革により、木造中学校は木造高等学校となり、講堂も引き続き使用されました。 講堂の特徴としては、緑色の鉄板瓦棒葺きの屋根や、モルタル塗りの外壁、トラス構造の屋根骨組みなどが挙げられます。特に、トラス構造は西洋建築で発達したもので、屋根を支える柱が少なく済むため、広い空間を造り出すことができます。また、天井には2段の折上額縁天井が施され、中央にはシャンデリアを吊るすメダイオンが設けられております。 現在、旧制木造中学校講堂は、地域の生涯学習の場として、また地域振興の拠点として活用されております。市民のサークル活動や演奏会、講演会、懇親会など、様々な用途で利用されており、そのレトロな雰囲気が多くの人々に愛されています。見学も可能で、事前に予約をすれば団体での見学も受け付けています。 このように、旧制木造中学校講堂は、地域の歴史と文化を象徴する貴重な建造物として、今後も大切に保存され、活用されていくことでしょう。
-
- 前のページ
- 1
- 次のページ
■全国の博物館検索
ホームメイト・リサーチに
口コミ/写真/動画を投稿しよう!
「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。
Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん
- ゲストさんの投稿数
-
今月の投稿数 ―施設
- 累計投稿数
-
詳細情報
―件
口コミ
―件
写真
―枚
動画
―本